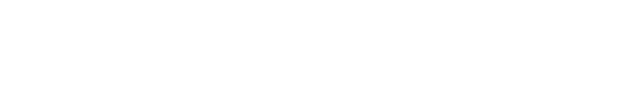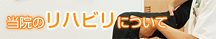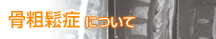骨ドック(保険適応)
骨粗鬆症検査と治療
骨粗しょう症とは
骨粗しょう症とは、
加齢によって
骨のカルシウム量などが減少し、
骨が非常にもろい状態となり
骨折しやすくなる病気です。
骨が完成されると
常に同じ状態と思われがちですが、
じつは
人の肌と同じように、
壊れて[骨吸収と言います]
そして
作られて[骨形成と言います]
を繰り返す
“新陳代謝”[リモデリング]
が行われているのです。
骨が壊れる働き[骨吸収]に
骨が作られる働き[骨形成]が
追いつかなくなることで
骨粗しょう症になるのです。
この一番の原因は
加齢によるものであり、
骨密度は若年期をピークとして
だんだん減っていき、
40代・50代を過ぎると
急激に減っていきます。
これには
ホルモンの変化が関係していますが、
女性では特に
女性ホルモン(エストロゲン)の減少が
骨粗しょう症を引き起こす
大きな要因になっています。
そのため、
骨粗しょう症の約8割が女性
といわれており、
60代女性の3人に1人、
70代女性の2人に1人が
骨粗しょう症とされています。
そのほかにも運動不足や喫煙、
飲酒、カフェインの摂りすぎなどの
生活習慣も関わっています。
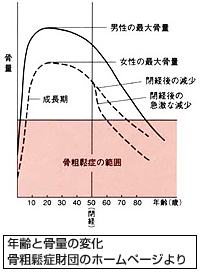
骨粗しょう症の症状
骨粗しょう症の代表的な症状は、
骨折とそれによる痛みです。
そのため骨折するまで
骨粗しょう症であることに気付かない
患者さんがほとんどです。
代表的な骨折の部位としては
- 太ももの付け根
- 手首
- 腰
で、その多くは
転んで強く地面に打つことで起こります。
骨粗しょう症による骨折は
寝たきりになる原因の第2位
となっています。
またある調査によれば、
骨粗しょう症で
太ももの付け根の骨折(大腿骨頚部骨折)
を起こした人の
5年生存率は50%
というデータがあり、大変深刻な病気です。
また
「年のせいで背中が曲がってしまって…」
「最近背が低くなったみたい…」
と言われる方の大半も
骨粗しょう症によるものと考えられます。
これは、
もろくなった背骨や腰骨が、
悪い姿勢や重たいものを持つ衝撃により
押しつぶされることで起こってきます。
骨粗しょう症の検査
当院では、以下の方法を用いて、
骨粗しょう症の早期診断・治療に
力を入れております。
- 骨密度の測定(DXA法)
現在の骨密度の予測
最も信頼性が高く、
短時間で正確に測定ができます。
2種類のX線を体の部位に当て、
透過率の差で骨密度を計測します。
放射線の量も
一般のレントゲンと比べて
ごくごくわずかなので、
安心して行っていただけます。
富士フィルム株式会社HPより
腰椎・大腿骨頚部も測定できる全身用骨密度検査(DXA法)をご希望の方は
当院から徒歩1分の分院「ふじいリウマチ・骨・関節クリニック」の受診をご検討ください分院のHPはこちらをクリック
- 骨代謝マーカーの測定
将来の骨密度の予測
血液検査・尿検査により測定され、
骨の新陳代謝の速度を
知ることができます。
骨吸収(壊れる働き)を示す
骨代謝マーカーの高い人は、
骨密度の値にかかわらず
骨折の危険性が高くなります。 - 体重・身長測定
体重が 年齢-5kgより軽い方、
若い頃より
4cm以上の身長短縮がある、
亀背などがある方は
骨粗しょう症の疑いがあります。
上記検査を行うことをおすすめいたします。 - 骨粗しょう症のチェック表
骨粗しょう症のチェック表をご紹介します。
該当する項目が多い方は、
骨粗しょう症検査をしてはいかがでしょうか?
| 骨粗しょう症チェック表 | |
| □ | 最近、背が縮んだ |
| □ | 最近、背中が丸くなったり、腰が曲がってきた |
| □ | ちょっとしたことで骨折した |
| □ | 体格はどちらかというと細身だ |
| □ | 卵巣、精巣、消化器、甲状腺の手術歴がある |
| □ | カフェインをよく摂取する |
| □ | アルコールをよく飲む |
| □ | 愛煙家である |
| □ | 無理な食事制限でダイエットをしたことがある |
| □ | 運動不足である |
| □ | 天気の良い日でも外に出ない |
| □ | ご家族で骨粗しょう症と診断された方がいる |
| □ | 閉経を迎えた(女性のみ) |
| □ | 過去生理不順であった(女性のみ) |
| □ | 出産している |
| □ | 70歳以上である |
骨粗しょう症の治療
-
薬物療法
運動や食事は
骨粗しょう症の予防に欠かせませんが、
1番はお薬による治療になります。
骨粗しょう症のお薬は作用によって
次の4種類に分けられます。- カルシウム剤
- 骨吸収を抑制する薬剤
ビスフォスフォネート
エストロゲン
カルシトニン
SERM - 骨形成を刺激する薬剤
蛋白同化ホルモン
副甲状腺ホルモン - 上記のいずれにも分類できない薬剤
活性型ビタミンD3
イプリフラボン
ビタミンK2
- 食事療法
- カルシウム(骨量の維持、増加を助ける)
- ビタミンD(カルシウムの吸収を助ける)
- ビタミンK(骨に必 要なたんぱく質をつくる)
など、骨に必要不可欠な栄養素を
なるべく採りましょう。
他に
-
- マグネシウム
- ビタミンC
- ビタミンB
なども必要な栄養素です。
カルシウムの1日の摂取目標量は
800mg以上です。
牛乳100gでカルシウム約100mgなので、
乳製品が苦手な人には
結構な量と思われがちですが、
豆腐や納豆などの大豆製品にも
たくさん含 まれているので、
それらをバランス良く摂るようにしましょう。
また、過度なアルコールやカフェインの摂取は
尿へのカルシウムの排出量を増やし、
喫煙は胃腸の働きを悪くし
カルシウムの吸収を妨げます。
これらの嗜好品は、
なるべく控え目にしましょう。
-
- カルシウムを多く含む食材
乳製品、干しエビ、
小松菜、チンゲン菜、
大豆製品など
-
- ビタミンDを多く含む食材:
サケ、ウナギ、サンマ、
カレイ、シイタケ、キクラゲなど
-
- ビタミンKを多く含む食材:
納豆、ホウレン草、小松菜、
ニラ、ブロッコリー、レタスなど
- 運動
運動により骨に荷重がかかり
骨密度の低下を防ぐことができます。
また筋力がつきバランスも養われるので
転倒を防ぐことができ、
骨折のリスクを軽減します。
運動が苦手な人も、
歩いて近所へ買い物に行ったり
エレベータをやめて階段にするなど、
今より少し
運動量を増やすことから始めましょう。
また、日光浴によって
皮膚でビタミンDが作られます。
ビタミンDは
腸管からのカルシウムの吸収を促進させ、
かつ
カルシウムの骨へ吸収を促進させます。
しかし、
過量な紫外線は
皮膚がんの発生リスクを高めますので、
夏は木陰で30分、
冬は手や顔に1時間程度で
十分です。
高血圧や糖尿病、心臓疾患等の既往のある方は、
ご自身に最適な運動を
医師・専門家の指示の下行ってください。
まとめ
どうすれば骨を強くできるかをまとめると、
- 定期的に検査を受けて治療する
- カルシウムとたんぱく質をとる
(乳製品・大豆製品、肉・魚) - 天気の良い日に外で適度な運動をする
- お酒を飲みすぎない
タバコ・コーヒーを控える
などが挙げられます。
骨粗しょう症が心配される年齢になれば、
積極的に検査を受け治療することで、
将来の寝たきり予防になります。
またそれにより、
骨折の心配のない健康な体を手に入れ、
いつまでも心身ともに
充実した生活を送ることが、
骨粗しょう症治療の
最大の目標となるのです。